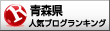西目屋村の道の駅「津軽白神」で開催された「着飾るこぎん展」の最終日に出かけて、先生のワークショップに参加できたので、刺し終えたランチョマットとともに、お伝えします。
スポンサーリンク
天然本藍染

画像をお借りしました。
TOP | 津軽天然藍染川﨑染工場/Tsugaru Natural Indigo Dyeing Store
弘前市紺屋町にある津軽天然藍染 川崎染工場は明治時代からの藍甕(あいがめ)で、藍を発酵させている歴史的なお店&工房。
私は2回ほど見学しました。
展示室には古作こぎん衣もあります。

深い色味で濃淡3色。
去年、購入したセットのなかに入っていたので、刺したのです。
完成まで、1か月くらいかかりました。
ところで藍は江戸期に農民に許された唯一の色。
植物の藍の葉を発酵させて発色させます。
ちなみに万札の顔・渋沢栄一の実家は、農家のほか藍の産業を営み、富を築きました。
蝶のモドコ

ひと針ひと針、丁寧に刺しましたが、針目が揃っていないところもあります。
真ん中は蝶のモドコ。
こぎん刺しは森羅万象や、身近な昆虫や動物の足跡などをモチーフにした文様(もどこ)が多いです。
「あら、出来たの。藍のグラデーションね」
陽子先生に見て頂きました。
「刺しっぱなしでなく、ふちを青い布でかがるとよいですよ」と、陽子先生。
ありがとうございます🌸
スポンサーリンク
こぎん文様Tシャツ

私は白を持っています。
古作こぎんの紋様をプリントした佐藤陽子オリジナルこぎんTシャツ。
こちらは、弘前市立観光館で撮影。
着やすい綿100パーセントのTシャツ、こぎん文様がうれしい。

陽子先生のこぎん糸は12本どり。
作品は豪華に見えると評判です。

外崎さんは青森市から受講されてます。
ベスト完成、すばらしい。

最終日なので、紬に自作のこぎん帯で参加。
陽子先生、お目にかかった皆様ありがとうございます。
まとめ
私にとってのこぎん刺しとは、雪国の女性の生き方を体感すること。
みなさんの布目を拾って刺し綴る根気強さにいつも、感服しています。
天然本藍のこぎん糸で刺した作品を中心にお伝えしました。
スポンサーリンク